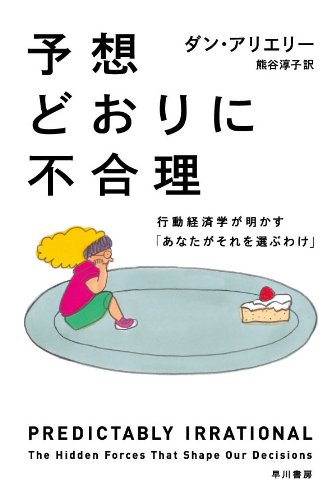- Published on
なぜ、あなたのメルカリは「希望価格」で売れないのか?〜自分のモノを過大評価する『保有効果』の呪い〜
ざっくり言うと
- フリマアプリで自分の古着が思った値段で売れないのは、あなたがその価値を無意識に過大評価してしまう「保有効果」の呪いにかかっているからだ。
- ダン・アリエリーの「マグカップ実験」が示すように、一度自分のものになると、売り手と買い手の間には絶望的な価値観のズレが生まれる。
- この呪いを解く鍵は、「もしこれを持っていなかったら、今いくらで買うか?」と自問する「仮想の非所有」の視点を持つことだ。
はじめに:その「美品」、本当に価値がありますか?
クローゼットの整理を決意し、意気揚々とフリマアプリに数年前に買った服を出品する。「着用回数も少ない美品だし、元は高かったから…」と、あなたは少し強気の値段をつけた。しかし、何日経っても「いいね」は付かず、たまに来るのは大幅な値下げ交渉ばかり。あなたはこう思うのではないだろうか。「この価値がわからないなんて、見る目がないな」と。
残念ながら、見る目がないのは相手ではなく、あなた自身かもしれない。ダン・アリエリーが『予想どおりに不合理』で明らかにしたように、我々は一度何かを「所有」した途端、その価値を客観的に判断できなくなる。これが「保有効果」と呼ばれる、根深い心のクセなのだ。
マグカップ実験:持ち主と買い手の絶望的な価値観のズレ
この効果をシンプルかつ強力に示したのが、アリエリーが行った「マグカップ実験」だ。彼は、大学のロゴが入ったごく普通のマグカップを使い、学生を二つのグループに分けた。
- グループA(売り手): 最初にマグカップを与え、「いくらなら売るか?」と尋ねる。
- グループB(買い手): マグカップを与えず、「いくらなら買うか?」と尋ねる。
論理的に考えれば、同じマグカップなのだから、両者の価格は近いはずだ。しかし、結果は驚くべきものだった。
売り手(グループA)の提示額の中央値が5.75ドルだったのに対し、買い手(グループB)の提示額の中央値は、わずか2.25ドル。一度「自分のもの」になったマグカップは、持ち主にとって特別な価値を持つ「宝物」へと変貌し、客観的な価値の2倍以上の値段がつけられてしまったのである。
なぜ、自分のモノだけが輝いて見えるのか?
アリエリーは、この奇妙な心理が生まれる理由を、人間の根源的な「損失回避性」と関連付けて説明している。人間は、何かを得る喜びよりも、何かを失う痛みを2倍以上強く感じるようにできているのだ。
売り手(持ち主)の心理: マグカップを手放すことは、「自分の所有物を失う」という痛みを伴う。そのため、その痛みを補って余りある高い金額でなければ、手放そうとしない。
買い手の心理: マグカップを手に入れることは、「単に一つのモノを得る」という喜びでしかない。失う痛みがないため、冷静にそのモノの価値を判断し、安い価格を提示する。
さらに、持ち主はマグカップにまつわるポジティブな記憶(大学生活の思い出など)に焦点を合わせるが、買い手は他のマグカップとの比較や欠点に目を向ける。この視点のズレが、絶望的な価格差を生むのだ。
【改善案】フリマアプリで使える「仮想の非所有」思考法
このやっかいなバイアスから逃れ、適正な価格で「売れる」ようになるための方法は、アリエリー自身が示唆している。「仮想の非所有」という考え方だ。フリマアプリで値段を付ける前に、次のように自問してみるのだ。
「もし、私がこれを持っていなかったとして、今、この状態の同じものがタイムラインに流れてきたら、いくらまでなら即決で買うだろうか?」
この問いは、あなたを一時的に「買い手」の立場に立たせ、感情的な愛着や失う痛みから切り離してくれる。この心理的な距離を置くことで、より客観的で、市場が受け入れる価格に近い判断を下しやすくなるだろう。
おわりに:その「こだわり」、本当に価値がありますか?
保有効果は、モノの値段付けだけの話ではない。我々が固執する「自分の意見」や「昔ながらのやり方」もまた、この効果に強く影響されている。長く持ち続けているというだけで、我々はそれを過大評価し、手放すことに過剰な痛みを感じてしまう。
自分の持ち物、自分の意見、自分のキャリア。それらを一度、「仮想の非所有者」として眺めてみてはどうだろうか。そこには、あなたが思っているほどの価値はないのかもしれない。そして、それを認めることこそが、新しい価値を手に入れるための第一歩なのである。
【行動を促すためのアクション】 なぜ、返金保証付きのソファを買うと、ほとんどの人が返品しないのか?その答えも『予想どおりに不合理』にあります。所有という感情が我々の判断をいかに歪めるか、本書でその深淵を覗いてみてください。数々の巧妙な実験が、あなたの「当たり前」を覆してくれるはずです。