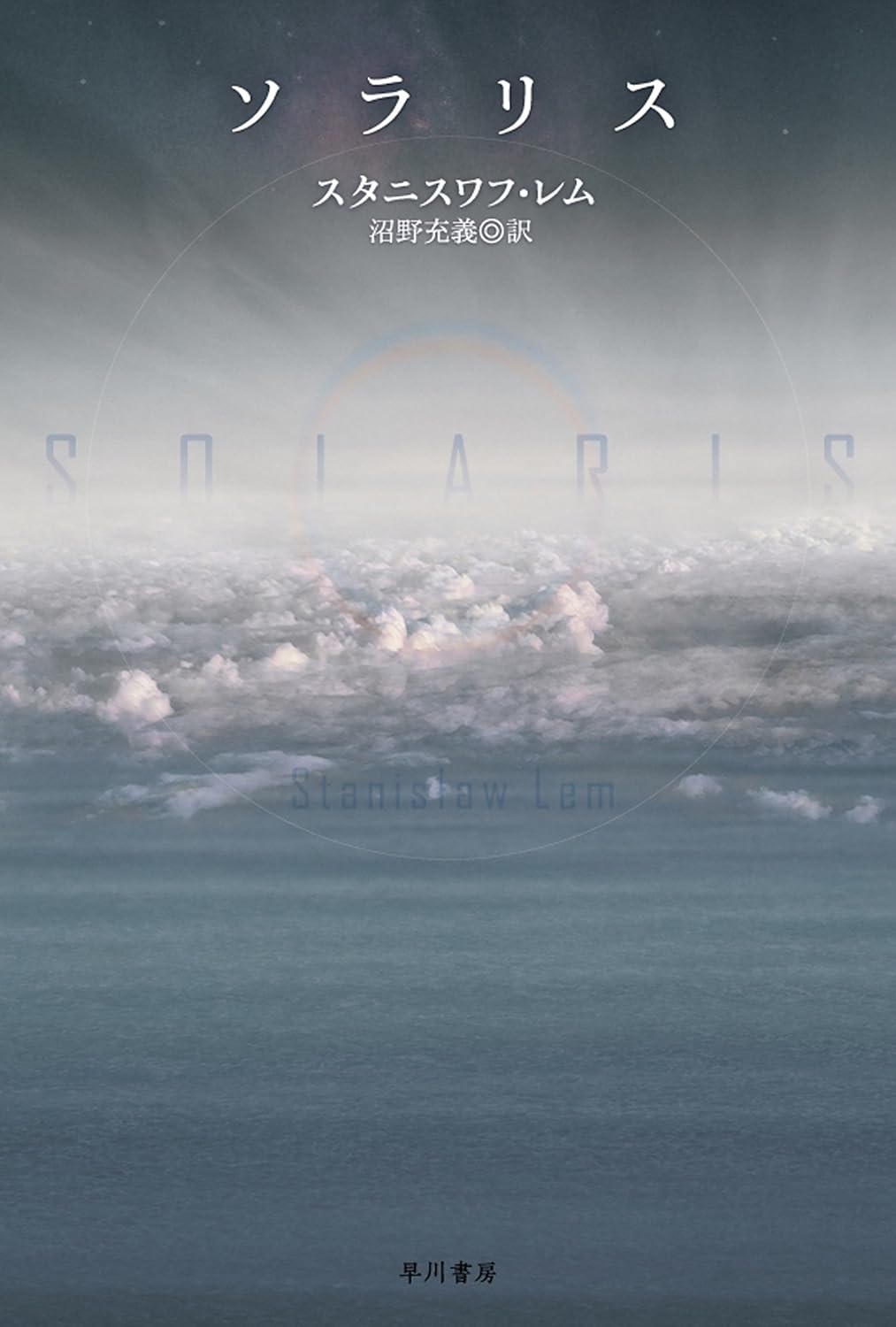- Published on
「テレビを生やす遺伝子」はSFじゃない? レムの奇書『技術大全』の狂気に山形浩生と迫る
ざっくり言うと
- レムは「材料を与えるとテレビが勝手に生えてくる遺伝子」というアイデアを、SFではなく実現可能な科学技術として大真面目に論じていた。
- この狂気の書『技術大全』は、SFが裸足で逃げ出すレベルの思考実験の塊であり、レム思想の中核(マザーシップ)である。
- 翻訳者・山形浩生氏の解説が、この奇書のヤバさと面白さを余すところなく伝えてくれる。
はじめに:「テレビが勝手に生えてくる」は科学である
「適切な材料を与えたら、そこからテレビが勝手に生えてくる。そんな遺伝子を作れないか?」
もしあなたがこんな話を聞いたら、間違いなくSFの世界だと思うだろう。だが、これをSFではなく「科学的考察だ」と言い張った男がいる。『ソラリス』で知られるSF界の巨匠、スタニスワフ・レム、その人である。
彼の著書 『技術大全』 は、タイトルに反して、そんな狂気の思考実験をどこまでも大真面目に論じ尽くした、とんでもない奇書だ。これは単なるノンフィクションではない。我々の常識を根底から揺さぶる、知の暴力である。
最近、翻訳家の山形浩生氏が、AIの力を借りて本書の全訳を公開した。その熱量あふれる「訳者解説」を読むだけでも、この本のヤバさがひしひしと伝わってくる。今回はその解説を手がかりに、この狂気の書物の正体に迫ってみたい。
『技術大全』は何が「大全」なのか?
本書の核心的なアイデアは、恐ろしくシンプルでありながら、恐ろしくクレイジーだ。そしてレム自身は、それを至って真面目な「科学的考察」だと信じていた節がある。
生物進化と技術進化を「ガチで」接続する思考実験
「技術進歩を生物進化みたいにできないか?」――ここまではよくある話だ。多くの凡人が口にする安直な比喩である。だがレムは、常人の思考を遥かに飛び越えていく。
「自然進化みたいにするなら、技術を遺伝子もどきに符号化して翻訳したいよね、それも、紙に仕様書や理論を書くんじゃなくてさ、その仕様をコーディングした遺伝子もどきに適切な材料をやると、そっからテレビが勝手に生えてくるようにしよう!」てな馬鹿なことを考え出す。「それでさ、その遺伝子もどきを突然変異させて競争させると、技術が自動的に進歩するじゃん!」
スタニスワフ・レム『技術大全』訳者解説 - 山形浩生の「経済のトリセツ」より引用
彼は、エンジニアリング的な設計図や仕様書に基づくトップダウン的な開発ではなく、ボトムアップで、自己組織的にプロダクトが「発生」する仕組みを構想した。そのお手本が、生物の遺伝子(ゲノム)だ。遺伝情報というただの文字列が、適切な環境(生体内の化学反応)さえあれば、タンパク質を作り、細胞を作り、果ては人間という複雑なシステムを「生やして」しまう。この自然界の奇跡を、人工物で再現しようというのである。
もちろん、山形氏が指摘するように、この構想の最大のネックは「どうやってそんな遺伝子もどきを作るんだ?」という点に尽きる。レムはその具体的な実装方法については深く語らない。彼はむしろ、「生物の遺伝子は現にそれができているじゃないか。ならば、他のものでできない理由はないはずだ」という、ある種の開き直りにも似た論理でその実現可能性を主張する。この、工学的設計の困難さを「自然界の成功事例」という巨大な事実で飛び越えてしまう点こそが、レムの思考の「狂気」と「凄み」の源泉なのである。
「情報農場」:理論すらも自動生成する世界
この狂気は、ハードウェアとしての技術だけでなく、ソフトウェアである「科学理論」にまで及ぶ。彼は、科学の発展そのものも、この進化のプロセスに載せて自動化できると考えた。
「だからさ、科学理論だって理論を遺伝子もどきに翻訳/符号化すればいいよね、そしてその遺伝子もどきが変異して競争するようにすれば、勝手に理論が湧いてくるの! 情報農場だ! そしてそっから出てきて勝ち残った遺伝子もどきを復号すると、新理論いっちょあがりってわけよ!」
同上
まだ分かりにくいと思うので、思考実験をしてみよう。例えば、アインシュタインがいなくても「情報農場」が相対性理論を発見するプロセスはこうだ。
「遺伝子」を用意する: まず、既存の物理学の法則や数学の公式、物理定数などを「遺伝子」として符号化する。ニュートンの運動方程式
F=maや万有引力の法則F = G*(m1*m2)/r^2、あるいは「光の速度は不変である」といった命題が、それぞれ一個の遺伝子になる。「個体(理論)」を生成する: これらの遺伝子をランダムに組み合わせて、無数の「個体」、すなわち「物理理論の仮説」を生成する。ある個体はニュートンの法則だけを持ち、別の個体は万有引力の法則と「空間は歪む」という遺伝子を偶然持っているかもしれない。
「環境(実験データ)」で淘汰する: 次に、これらの無数の理論仮説を、「環境」に放つ。ここでの環境とは、実際の観測データや実験結果のことだ。例えば、「水星の近日点の移動が、ニュートン力学では説明できない」という観測データが、理論の生存を試す「淘汰圧」になる。
「進化」させる: この環境にうまく適合できた理論(=観測データをより正確に説明できた理論)だけが「生き残り」、次世代の遺伝子を残す権利を得る。生き残った理論の遺伝子同士をさらに交配させ、突然変異を起こし、また新しい理論仮説の集団を作る。このプロセスを何百万世代と繰り返すのだ。
このプロセスを経れば、人間の天才的なひらめきがなくても、淘汰と進化の力学だけで、やがてはアインシュタインの一般相対性理論に極めて近い理論体系が「発見」されるかもしれない。レムは、人間の思考を介さずに理論や思想そのものが自動生成される、そんな未来の可能性に60年以上も前にたどり着いていたのである。
山形浩生が「訳すしかなかった」理由
では、なぜこんな重要作が今まで本格的に訳されてこなかったのか。山形氏の解説はその理由も雄弁に物語る。
半分以上が「脱線」という奇妙な構造
本書は、本筋と全く関係のない「脱線」に満ち満ちている。宇宙人とのコンタクトの可能性を30ページかけて論じた挙句、「まあ、参考になる事例はないんだけどね」で締めたり、AIの危険性を語っていたはずが、いつの間にか宗教論や精神分析批判に突入したり。
山形氏はこの読書体験を「行き倒れというか徒労感」と表現するが、同時に「それがまさにこの本の醍醐味でもある」と語る。この支離滅裂で、どこまでも思考をさまよわせるスタイルこそが、レムの知性のあり方そのものなのだろう。
この本を読まずしてレムは語れない
山形氏は断言する。「本書を参照せずに書かれた幾多のスタニスワフ・レム論は、ほぼゴミクズとさえ言えなくもない」と。
なぜなら、『ソラリス』の異質な知性も、『電脳の歌』のロボットの世界も、全てはこの『技術大全』で展開された思考実験の「小説的表現」に過ぎないからだ。レムにとってSFとは、単なるフィクションではなく、現実になりうる可能世界の探求だった。その根幹にある思想を知らずして、彼の作品を本当に理解することはできない、というわけだ。
結論:我々はレムの「幻影環境」を生きている
『技術大全』は、単なる技術予測の本ではない。それは、技術と生命、情報と物質の境界を溶かし、知性そのものの可能性と限界を探る、壮大な思考の迷宮である。
レムは本書で、現実と区別のつかない「幻影環境(ファントマティクス)」についても論じている。VRやメタバースが現実になりつつある今、我々は知らず知らずのうちに、レムが60年前に描いた世界に足を踏み入れているのかもしれない。
この本を読むという体験は、我々の凝り固まった思考を揺さぶり、知性を試すリトマス試験紙のようなものではないだろうか。山形氏のおかげで開かれたこの巨大な知の迷宮に、あなたも足を踏み入れてみてはいかがだろう。